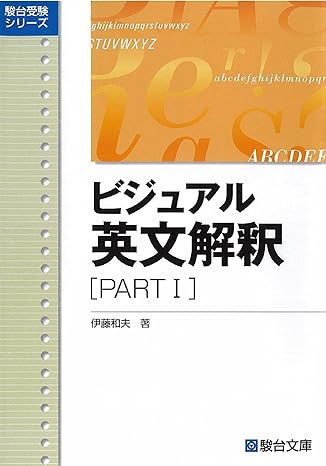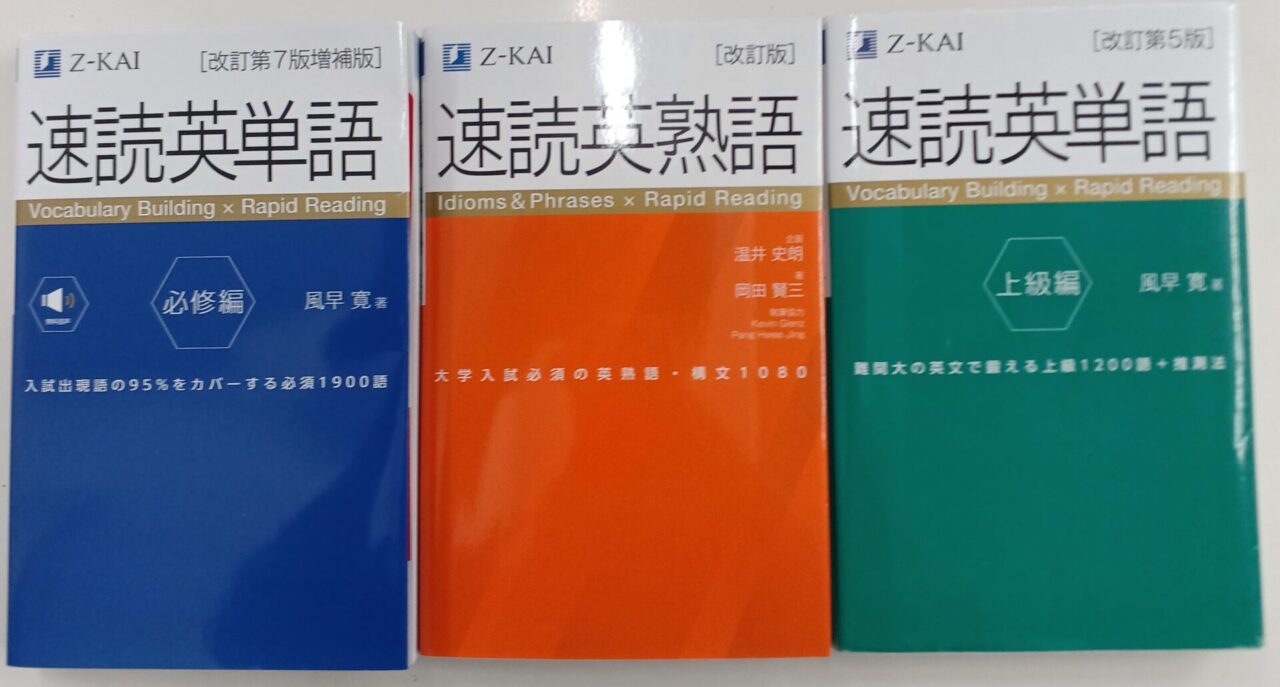
目次
0 はじめに
1 速単シリーズの特徴
2 速単シリーズの使用法
3 必修編の補足
4 速熟の補足
5 上級編の補足
はじめに
いきなりですが、実は、私は速単ファンなのです。
伊藤和夫の『ビジュアル英文解釈』はすごいなという感じなのですが、速単は大好きです。
私どもの塾では高1・高2生に『ビジュアル英文解釈』と速単シリーズの必修編・速熟・上級編に取り組ませていますが、英語の成績が爆上がりしてしかたありません。
『ビジュアル英文解釈』と速単シリーズの組み合わせは最強です。
『ビジュアル英文解釈』で英文を左から右へ流れのままに読む方法を学び、速単シリーズでその訓練をしながら、語彙力をつけることもできるのです。
今回は速単シリーズの特徴と使用法を説明させていただきます。
1 速単シリーズの特徴
速単シリーズの最大の特徴は単語・熟語を英文の中で覚えるという形をとっているところです。
私のように単語帳で単語を覚えるのが苦痛でしかたないという人には神のような教材です。
まず単語帳で単語を覚えた後、速単シリーズを使うことを勧める人もいますが、私はお勧めしません。
それだと二度手間になりませんか?
最初から英文の中で覚えた方が効率がよくないですか?
入試では単語ではなく、英文が出題されます。
単語を覚えるというのはあくまで手段で、目的は英文を読めるようになることです。
ならば、不要なステップは飛ばした方が効率がよいでしょう。
単語帳で単語を覚えると、1つ1つの英単語の意味を日本語に変換し、その総和から英文全体の意味を推測するということになりがちです。
しかし、単語の意味の総和が英文全体の意味となるとは限りません。
単語の意味は英文全体の文脈から決まるものです。
日本語の文章を読むときに1語1語の意味をいちいち考えませんよね?
文もしくは段落などのかたまりごとに意味を理解しているはずです。
英文を読む場合も同じです。
実際には、語彙力のない生徒は単語帳を使った方が短い時間で語彙力をつけることができるという面もあります。
よって、私どもの塾でも、単語帳を使うことを禁止にはしていません。
ただ、単語帳を使った場合、上記の理由から、どうしても英語力が伸び悩んでしまいます。
速単シリーズの第二の特徴は、入試頻出のトピックを扱った英文を読むことができることです。
最終目的は、英文理解=内容理解です。
英文の形を把握できることも必要ですが、入試頻出の内容になじんでおくことも同じくらい必要なことです。
まさに一石二鳥、一石三鳥の教材が速単シリーズなのです。
2 速単シリーズの使用法
速単シリーズの使用法です。
1 まず英文を読んで下さい。
和訳は不要です。
英文を左から右へ流れのままに読み進め、意味が理解できるかどうかを試して下さい。
2 和訳ページ・英文解説ページ・解説映像・単語ページを使って、意味が理解できない箇所を意味が理解できるようにしましょう。
3 単語ページを熟読して下さい。
単語を覚えなくてかまいません。
熟読するだけでかまいません。
4 英文を意味を考えながら繰り返し読んで、聞いて下さい。
その際、単語ページも再度熟読して下さい。
中学版と入門編は、取り組むなら、中学生の間にすませておきましょう。
必修編・速熟・上級編は、あくまで理想ですが、高校3年間1000日で1日1文ずつ、3冊200文を5周しましょう。
5周すれば、単語帳に取り組まなくても、入試に必要な語彙力はつきます。
後は入試問題をどんどん読んでいくだけで大丈夫です。

3 必修編の補足
必修編には「速単の英文で学ぶ英語長文問題70」というものがあります。
必修編の英文を題材とした長文問題集です。
また、ディクテーションのページもついています。
これらがなかなかいいのです。
もちろん復習教材としてよいですし、解答編には見やすい構文分析がありますので、英文の理解も深まります。
速単ファンからZ会へのお願いです。
ぜひこれらの速熟版・上級編版を作って下さい!
4 速熟の補足
熟語・構文・語法は入試では重要です。
単語の方が気になるかもしれませんが、実は、最終的には、熟語・構文・語法の方がネックになるからです。
また、速熟は文法の要点をまとめたCheck&Masterがとてもよいと思います。
熟語・構文ページにリンクがはってありますので、積極的に活用して下さい。
5 上級編の補足
上級編の目的は必修編の復習+未知語の意味を推測する訓練です。
必修編だけで大学入試に出てくる単語の95%をカバーしてくれていますが、どんな単語帳を使っても、100%をカバーすることはできません。
よって、未知語の意味を推測する訓練は、単語を覚えることよりも大事だとも言えます。
推測で学ぶ接頭辞・接尾辞、まとめてチェック、カタカナ語チェックのページは熟読して下さい。
冒頭に掲載されている推測原則、接頭辞・接尾辞のページも積極的に活用しましょう。
ただ、語源の学習は別教材で補った方がよいでしょう。
語源の知識があると、未知語の意味の推測ができるようになります。